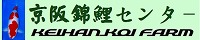|
|
錦鯉を飼う最大の目的は、まずは健康に育成することであります。
そのためにはまず、その対策を講じることから始めます。それには各々様々な工夫が凝らされていますが、
健康で、なおかつ錦鯉(観賞魚)である以上鑑賞に支障のない池造りでなければなりません。
池は錦鯉が生活する場所なので、錦鯉にとって住みやすい居住空間を最優先に考えてゆく必要があります。
ここでは、自然環境の池は考えに入れず、錦鯉の生態・飼育水の性質に重点をおき、一般的なコンクリート池・水槽での考えをまとめます。
|
|
|
 池の形状は、どのような形でも構いませんが、 池の形状は、どのような形でも構いませんが、
水が滞留してしまうような複雑な形状は好ましくありません。
錦鯉を飼育する上で、一番重要なことは水質の管理なので、
管理しやすい形にしておくことが望ましいでしょう。
池のコーナーは水が回転しやすいように丸みを持たせて、
角を造らないように考慮します。
特に和風の場合は特に形状が複雑になりやすいので、
池の中に石組は行わず、池の縁にとどめておけば
景観はさほど気になりません。
 
 
池の大きさは沈殿槽・濾過槽を考慮して、できるだけ大きく取った方がよいでしょう。
いったん池を造ってしまえば、容易には造り直せませんし、
錦鯉を飼育するうちに、いずれいろいろな品種が欲しくなり、錦鯉も成長します。
池はすぐに手狭になります。過密飼育になると、池は病原菌の巣窟になりかねません。
大は小を兼ねるとも言います。将来のことも考えて、できる限り広く取りましょう。
|
|
|
|
・水深30~70cm

池の水深が浅いために昼夜の水温差が大きくなる・水質が安定しづらい。
鷺や猫などの外敵に狙われやすいので、ストレスが加わりやすいです。
錦鯉のための水深ではなく、人間の都合(人が落ちたら危険・掃除がラク)によるものです。
・水深100~150cm
  

一般的な鑑賞池では理想的な池水の深さです。
ゆったりと錦鯉を泳がせることができます。
錦鯉が一番見やすく、鷺や猫などの外敵にも心配なく済みます。
錦鯉も掬いやすく、落ちた物や、ごみも取りやすいです。
水温の変化が少なく一番安定しています。
池が深いと、池底が見えないのではないかと思う人がいます。
水造りのしっかりした池では、底まで、しっかりと見ることができます。
・水深180cm以上
 
 錦鯉マニアのジャンボクラスを飼育する方に多いです。 錦鯉マニアのジャンボクラスを飼育する方に多いです。
|
|
太陽光が一日中あたらない池では、色が褪めやすくなります。
水量が小さな池では日光が当たり過ぎると水温の上昇を招き、アオコの発生となりやすいので、
あまり直射日光を当てないように工夫し、調節しましょう。
水量が大きい池では、陽のあたり過ぎでは水温の変化も少ないので、あまり気にしなくてよい。
陽が当たると錦鯉の色が良くなります。
また樹木が近くにあると、枯れ葉が池に入って落ち葉すくいに悩まされることになるので、
樹木の配置に気をつけましょう。
|
|
|
錦鯉の安息場所をと考えて、池の中にU字溝や切り株を沈めるのは良くありません。
池の中に凸凹があると、錦鯉がくぼみに隠れたがる習性があります。
錦鯉が人に慣れにくくなるばかりか、ゴミや排泄物が溜まりやすい為、病気にかかりやすくなります。
また、U字溝や切り株のとがった部分で怪我をしやすく、傷が付くと病原菌に冒されやすくなります。
池の飾り・装飾は、水の上にすれば錦鯉がぶつかって怪我をすることはありません。
池にある程度の深さがあり、池縁で驚かすことなく、いつも静かに餌をやっていれば、錦鯉は次第に慣れてきます。
敷石
デザイナーや庭師はぽっかり空いた池の空間をうめつくすように砂利、玉石や五郎太石を敷き並べたがりますが、汚れが隙間に堆積し、メタンや硫化水素が発生、水質悪化や病気の原因となり景観上も良くありません。
石の下が真っ黒になっていることが良くあります、これは硫化水素によるもので水質的にも大変危険です。
池の中は錦鯉の習性や水質のことを考慮し、錦鯉が怪我しないよう、障害物(隠れ家)や敷石は入れません。
錦鯉鑑賞池は池そのものが目立つ必要はなく、何もいれないで良いです。
池はキャンバス、錦鯉は絵の具と化し、鑑賞池は素敵な動く絵画とするのが錦鯉鑑賞池の基本です。
|
|
|

生物濾過槽の場合、池の水量の20%の水量が必要です。できれば30%あれば理想的ですが、比率は大きいに越したことはありません。
大きければ大きいほど飼育水はより安定します。
池を造る場合、メインの飼育池ばかりに気を取られて大きくし、
実際に飼育水を濾過する生物濾過槽のスペースが小さくなってしまうケースを良く耳にします。注意しましょう
 近年、住宅事情などでスペースの取れない場合は、一般的な濾過槽に代わって 近年、住宅事情などでスペースの取れない場合は、一般的な濾過槽に代わって
強制濾過機スーパーマリンが、その一役を担っています。
この装置は物理濾過と生物濾過を一緒に行うシステムになっており、スペースも生物浄化槽より小さくてすみます。
レバーを操作するだけで簡単に逆洗・濾材洗浄が出来るようになっております。
非常にコストパフォーマンスに優れた装置です。

また、強制濾過機スーパーマリンと濾過槽を組み合わせて循環させると最も効果的な方法だといえます。
|
|
|
|
|
|
ひと昔前は濾材に砕石や・砂が多く用いられていたが、目詰まりが多く掃除も大変なので、
現在で様々な形で開発された濾材が登場しています。
濾過槽内の濾材は、バクテリアをより、多く付着させる為、表面積の多い物を選び、
掃除のしやすい(洗いやすい)物を使用することが大切です。
|
|
|
|
|
池の水換え??
今は濾過設備が大変良いものがありますので、全面的な池掃除、大量の換水の必要はなくなりました。
大量の換水や、池掃除は水質も急変・移動の為に錦鯉を傷めますので、行いません。
差し水と言って常時、少量の新水を注水する方法を取ります。
硝酸
錦鯉が排泄するアンモニアを無害化するため、濾過機や浄化槽の中で好気性バクテリアを使って、
アンモニア→亜硝酸→硝酸へと変換します。硝酸は生物にとって、アンモニアや亜硝酸ほどではないのですが、
蓄積すると有害な物質となるので、池水量の1割の新水を常時補給する希釈操作(差し水)により、
硝酸濃度を飼育に適した許容値以下に制御します。
新水(差し水)
濾過・浄化を充実させると飼育水はこなれて透明になり、
錦鯉がすめる環境になりますが、PHは徐々に下がってきます。
濾過・浄化の最終物質の硝酸濃度が高くなり飼育水が劣化し、
泡立ち始めますので、新水によって溶け込んだ不純物を薄めます。
これにより飼育水を活性化させてくれます。
しかし、濾過・浄化が不十分で新水の注入が多すぎると、水がこなれず硬くなり、
鯉の色が仕上がらず、艶も落ちてきます。
逆に新水注入だけでは水は出来るどころか、大事な鯉の肌がかさつき艶も無くなります。
その辺が難しいところですが、新水の目安の量は1日に池の1割を入れるのが適量です。
例えば10tの池ですと1日に1tの新水が必要ということになります。
池の水源はどれが良いのでしょうか??
・河川水(オススメしません。)
河川水を使うと、農薬や除草剤、または生活排水など錦鯉にとって
有毒な物質が上流で混入する恐れがあります。
また、山間の谷川の水や渓流水は一般に硬度が高すぎて、
錦鯉の飼育水に適さない場合もあります。
常に河川水だけを流入させ、かけ流している池では、
錦鯉の肌が荒れやすく、色つやも良くなりません。
錦鯉を飼育するにはろ過設備によってコナレ水を造り、
栄養のたっぷり含まれた飼育水が不可欠ですが、
たいていの河川水は、錦鯉に適したコナレ水になってないことがよくあります。
・水道水(塩素に気をつければもっとも安全)<
塩素(カルキ)さえ注意すれば水道水は最も安全で使いやすい水源になります。
水道水には不純物が含まれておらず、蛇口をひねればすぐに調達でき、
水造りをする為の最適の条件を揃えた水といえます。
塩素を中和するには、中和剤のハイポを水10Lあたり2・3粒投入します。
水槽用として使用するなら、水槽のそばに一晩汲み置きしておけば、
塩素は飛んで、同時に水温も同じになります。
・地下水(大型の池では経済的)
10t以上の大型の池の場合は水道水では経費が高くついて、ままなりません。
そこで、大型の池では地下水を差し水として使用するところが多いようです。
水道水と大きな違いは、酸素が含まれていないことと、水温が年間を通じて15℃くらいですので
大量に使用する場合は、飼育池との水温差に注意し、爆気(エアレーション)をするなど気をつけます。
・雨水は(雨水は酸性)
雨水を新水として入れている池がたまに見られます。
最近の雨水は酸性(酸性雨)ですので、わざわざ毒水を入れていることになります。
大雨が降った後、水が綺麗になることがあります。それを見て飼い主は喜んでいることがあります。
それは比重の重い酸性雨が比重の軽い良い水を追い出し、池中が酸性の水でいっぱいになり、
水造りに必要なバクテリアを死滅させて、生き物が住めない環境になった悲惨な状況なのです。
錦鯉が必死の思いで最悪の環境に耐えています。
|